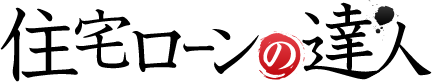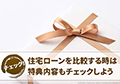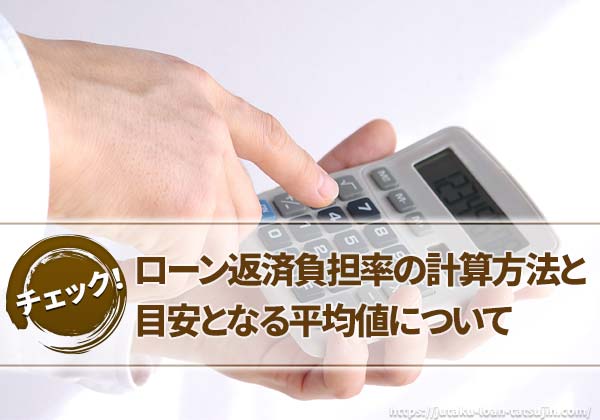
インターネットで住宅ローンについて調べる習慣がある人は、返済負担率という言葉を見聞きしたことがあると思います。
今回は実務でも頻繁に使われる返済負担率という言葉に焦点をあて、その使い方や活用方法についてみていきましょう。
返済負担率とは
住宅ローンの返済負担率とは、税込年収に対する総返済額の割合をパーセンテージで示したものです。
税込年収は分かると思いますが、返済負担率で使う総返済額は、住宅ローンのみの年間支払額を指すのではありません。
住宅ローンの返済に加えて、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードに付帯しているキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入)などの返済額も含みます。ここのところが、確実に浸透していない部分です。
住宅ローンを計画的に考えている方は、継続的なローンの利用残高を必要に応じてゼロにしているものです。最終的には年収とのバランスになりますが、マイホームのほかに自動車の購入をローンで考えている方は、マイホームの計画がすんでからにしましょう。
また返済負担率という数字は、不動産営業や建築営業マンも使いますが、本来は金融機関のほうで融資の判断基準に使う数字です。
返済負担率は非常にシンプルですが、住宅ローンの返済能力を見る際、どの人にも適合するという点で信頼をおかれています。
返済負担率の計算方法
それでは返済負担率の計算方法について説明していきます。
少し脱線してしまいますが、フラット35の申込要件のなかで、総返済負担率を使って利用基準を説明している箇所があります。
そこには、「年収400万円未満の方は年収に占める年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が30%以下、年収400万円以上の方は総返済負担率が35%以下」というフラット35の利用基準が示しています。
もちろん、この基準がすべての銀行の住宅ローンに用いられているわけではありません。年収の区分をもっと細かく分けているところもあるでしょう。ただ大雑把にいうと、年収を問わず総返済負担率が30%以下というところが大体の基準と考えて良さそうです。
計算方法と返済負担率の設定に注意
返済負担率は計算方法も非常にシンプルです。税込年収に対する年間総返済額の割合が返済負担率ですから、返済負担率を求める式は以下のようになります。
[年間返済額÷税込年収(万円)×100]=返済負担率(%)
ただし、上記計算式より、よく使う式が下記になります。
[税込年収(万円)×返済負担率(%)]=年間返済額
先ほどの基準を例に使うと、『[500万円×35%]=175万円』で、年間返済額が出てきます。ここから単月の支払額を出すと、『[175万円÷12か月]=約14.58万円』。これが毎月の支払額の上限です。
このように、折衝中の顧客の年収が判れば、どの程度の資金計画を持っていけば良いかが大体掴めます。
ただ、フラット35の利用基準の35%という数字は、それほど頻繁には使いません。というより、フラット35の申込要件で使われている返済負担率は、むしろ「幅を持たせている基準」と考えるべきでしょう。
税込年収500万円の方が毎月14、5万(返済負担率35%)返済することは無理ではありませんが、長く返すことを考えたら相当負担に感じるはずです。
フラット35の解説でも、よく読むと「年収400万円以上の方は総返済負担率が35%以下」としています。つまり、総返済負担率が35%となることを、それほど推奨しているわけではないということです。
自分のライフスタイルに合った返済負担率を
たとえば、この返済負担率を27%に設定した場合、計算式は省略しますが、返済負担率27%で、約11.25万です。
これでも子供の教育費にお金がかかる時期は危険ですが、毎月15万弱より返済額が4万円程度抑えられるので幾分かラクになります。
大体年収で500万という世帯は、筆者が現役の頃、返済負担率が20%~25%が限度と考えていました。25%を超える場合は、「家計が苦しい時、奥様がパートに出られるよう収入を調整する時期も出てくる」と助言していたと思います。
なお、土地込みで注文住宅を建てたり、新築で人気エリアのマンションを購入できる世帯は、返済負担率が30%を越すこともめずらしくはありません。ただ、そのうような物件を求める方は、夫婦共働きで世帯合算年収が1000万前後という方が多くなります。
もちろん、そのような世帯は返済負担率が35%以上であっても、ライフサイクルに関係なく毎月14、5万円の返済に十分耐えられます。もちろん、どちらが良いというわけではありません。ただ適切な返済負担率を設定するには、やはり経験のある方のアドバイスは必要でしょう。
金融機関は自社のローン審査に3%~4%の金利を使っている
ピークは過ぎたとは言え、住宅ローンは変動金利型を選ぶとまだ1%を割り込む超低金利です。返済負担率を用いた場合、金融機関が適用金利をそのまま流用することは考えにくいでしょう。
そのため銀行では、一般的に審査のための金利を設けています。これを「審査金利」などと呼んでいるのですが、その金利は3%~4%と言われています。なお、筆者自身は基準金利で再計算したものをお客様に説明していました。
とにかく、いくら適用金利が低かろうとも、それを用いて利用者に提示するのは大きな間違いです。勘違いしている営業マンもいますので注意してください。
なお計算方法ですが、[税込年収(万円)×返済負担率(%)]で年間返済額が算出され、これを12で割ると単月の返済額が出できます。
次に[単月の返済額]を[100万円当たりの毎月返済額]で割り、これに100万を掛けると[借入可能額]が算出できます。
「100万円当たりの毎月返済額(円)」を、表で簡易的に作成しましたので参考にして下さい。元利金等払いを条件としています。
| 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 5,984 | 4,598 | 3,768 | 3,216 | 2,822 |
| 1.50% | 5,907 | 4,825 | 3,999 | 3,451 | 3,061 |
| 2% | 6,435 | 5,058 | 4,238 | 3,696 | 3,312 |
| 2.50% | 6,667 | 5,299 | 4,486 | 3,951 | 3,574 |
| 3% | 6,905 | 5,545 | 4,742 | 4,216 | 3,848 |
| 3.50% | 7,148 | 5,799 | 5,006 | 4,490 | 4,132 |
| 4% | 7,396 | 6,059 | 5,278 | 4,774 | 4,427 |
借入の期間が30年で金利が2%だった場合、毎月返済額100万円あたり「3,696円」ですので、わかりやすく1,000万円を借り入れた場合には、「3,696円×10倍」で、毎月の返済額は「36,960円」となります。
計算例
[年間返済額]=150万円(年収500万の方が返済負担率30%の場合)
[単月の返済額]=12.5万円(150÷12か月)
[金利1%の場合の借入可能額]=約4429万円(12.5万÷2822×100万)
[金利3%の場合の借入可能額]=約3248万円(12.5万÷3848×100万)
返済負担率と返済比率の違いとは?
返済負担率と同じような言葉に「返済比率」があります。実際の仕事では、返済負担率と返済比率を明確に使い分けている人はほとんどいません。ただ、返済負担率と返済比率にはそれぞれ意味があります。
返済負担率とは、先ほども言ったとおり、税込年収に対する返済額の割合です。いっぽう返済比率の方は、金融機関等が定めた返済負担率の上限です。わかりやすく言うと、「年収が400万円以上の方は返済比率を25%までとする」といった場合に、返済比率という言い方を使います。
さらに、最近は使う人も減りましたが、返済負担率の別の言い方には「返済率」という言葉もあります。これも意味や使い方は、返済負担率と同じように使っています。
もちろん一般の方は、それほど神経質に使い分けなくても困ることはありません。返済比率を使い分ける場合は、そのような意味があることは覚えておくと良いと思います。
返済負担率の平均値
「フラット35利用者調査」に、返済負担率の平均値が出ているデータがありましたので抜粋してみました。
| 建物種別 | 全国 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文住宅(土地付き) | 単月返済額(千円) | 109.5 | 129.5 | 112.5 | 114.4 | 98.2 |
| 総返済負担率(%) | 23.3 | 24.3 | 24 | 23.8 | 22.5 | |
| 建売住宅 | 単月返済額(千円) | 92.5 | 100.9 | 90.8 | 82.1 | 74.9 |
| 総返済負担率(%) | 21.4 | 22.1 | 21.7 | 20.7 | 19.6 | |
| マンション | 単月返済額(千円) | 117 | 128.8 | 107 | 102.8 | 94 |
| 総返済負担率(%) | 21.1 | 22.4 | 21 | 18.9 | 17.5 | |
| 中古戸建 | 単月返済額(千円) | 68.2 | 80.4 | 62.8 | 59.1 | 57.1 |
| 総返済負担率(%) | 17.8 | 19.2 | 17.8 | 16.9 | 16.1 | |
| 中古マンション | 単月返済額(千円) | 80.1 | 86.6 | 69.1 | 56.3 | 60.6 |
| 総返済負担率(%) | 18.1 | 19.1 | 16.6 | 14.8 | 14.6 |
データを通して分かることは、返済負担率で30%を超えているところがないことです。25%を超えている箇所も見当たりません。中古ユーザーのなかには10%台のところも見受けられますが、それ以外は20%台前半です。
フラット35ですから、金利は21年目から微上昇するものの、それほど大きくは変わりません。それでも返済負担率をみなさんシビアに見ていることが分かります。
このデータは平均値を示していますから、なかには30%を超えて借り入れしている方もいるでしょう。ただその比率は、いずれの建物種別においても少数派であることは間違いありません。この事実は、これからマイホームを取得する方に有益な示唆を与えると思います。
返済負担率という言葉の意味や、活用の仕方について解説しました。おおよそ理解できたのではないでしょうか。
また返済負担率がむずかしい方は、いくらまでなら無理なく返せるのか、そこから返済額を見直してみるのも良いでしょう。その結果、我が家ではとても新築など無理と判断した場合は、中古市場(ストック)に目を向けるのもひとつです。
考えてみれば、どんなに新築が良くても、たった1日住んだだけでその建物はすでに新築の価値を失います。高い返済額に縛られるのが性に合わなければ、中古も魅力的な選択肢と言えるでしょう。
住宅ローンのおすすめの銀行
SBIマネープラザ(所属銀行:住信SBIネット銀行)

SBIマネープラザは金利が低いにも関わらず、保障が充実しているのが特徴です。一部繰上返済の手数料は何度でも0円。返済額は1円からでOKな点も魅力です。
しかも、ネットでの手続きだけでは不安な人向けに、来店予約をすればお金のプロが無料でアドバイスしてくれます。
万が一に備えて保障を充実させたい人や、住宅ローンの相談を直接窓口で行いたい人におすすめです。